
地域の保育園や幼稚園で働く看護師さんを対象に、医療的ケア児の理解と対応について研修会を開催しました。
講師は、PARCウィル東大阪で働く看護師・保育士・理学療法士が務め、医療的ケア児への保育と療育の必要性についてお話しました。
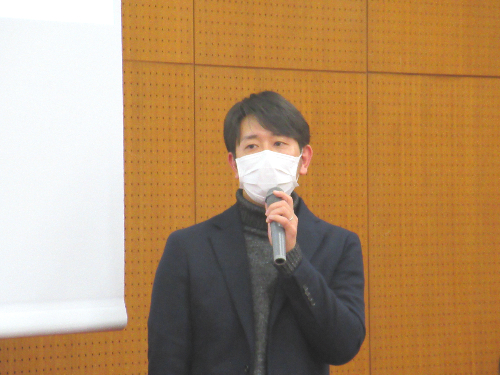
医療的ケア児を持つ保護者としての当事者視点
PARCウィル東大阪の理学療法士 兼 営業所長であるYは、双子の医療的ケア児を持つ当事者でもあります。
障害のある子を持つ保護者が、どのように障害受容をしていくのか、そしてどのようなニーズを持ち、園やデイサービスに通っているのか。
また、家族内の立場によっても精神的な支えが違うこと、生活するうえでどのようなことに不安を感じているかについても知ってもらう機会にしました。
これまでに実際の経験といま現在の思いを伝え、当事者に対する理解を深めてもらえたと思います。

医療的ケア児への保育と療育の必要性
「医療的ケア児」や「重症心身障害児」と一言にいっても、それぞれに症状や特徴があり、また一人ひとりの性格も好みも発達段階も違います。
上述を前提に、「保育」と「療育」の違いと共通点について知ってもらい、さらに医療的ケア児への「保育」と「療育」の必要性について理解を深めてもらいました。

「保育」と「療育」の違いとは?
「保育」と「療育」には、
・対象
・目的
・ベースとする指針
・活動方針
の4つの違いがあります。
たとえば、保育の対象が「すべての子ども」であることに対し、療育は「発達に凹凸、遅れ、障害を持つ子ども」とされています。
また、目的にも大きな違いがあり、保育では「子どもたちの日常生活のケア・教育・社会性などを育むサポートをする」としており、療育では「個々のニーズに応じて長所を伸ばしながら課題を対処する」となっています。
これらの違いを理解しつつ、子どもたちが楽しく成長できるように、子どもたちに関わる大人が共通の目的意識を持って「保育」と「療育」をおこなうことが重要です。

医療的ケア児にかかわる関係機関との連携と各専門職の役割
上記でも少し触れたように、子どもに関わる大人たちが共通の目的意識をもつことが大切です。
そのために重要になってくるのが連携です。
それぞれの専門的(看護師・保育士・療法士)視点と知識をもって、「療育」と「保育」のの工夫について、実例を交えながら具体的にお話しました。


まとめ
今回はPARCウィル東大阪研修会「医療的ケア児の理解と対応~役割分担と連携~」をご紹介しました。
「保育」も「療育」も子どもの成長と発達を支援するために重要な役割を果たします。
PARCウィル東大阪では、関係機関との連携や各専門職の視点と知識をもってこれからも子どもたちが楽しく成長できるように支援を行っていきたいと思います。

.jpg)



.jpg)


.jpg)








